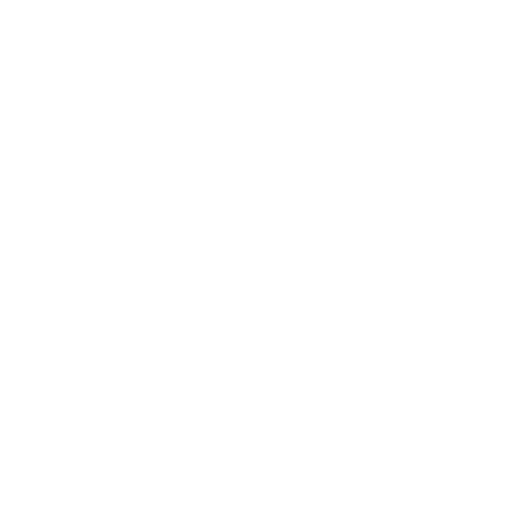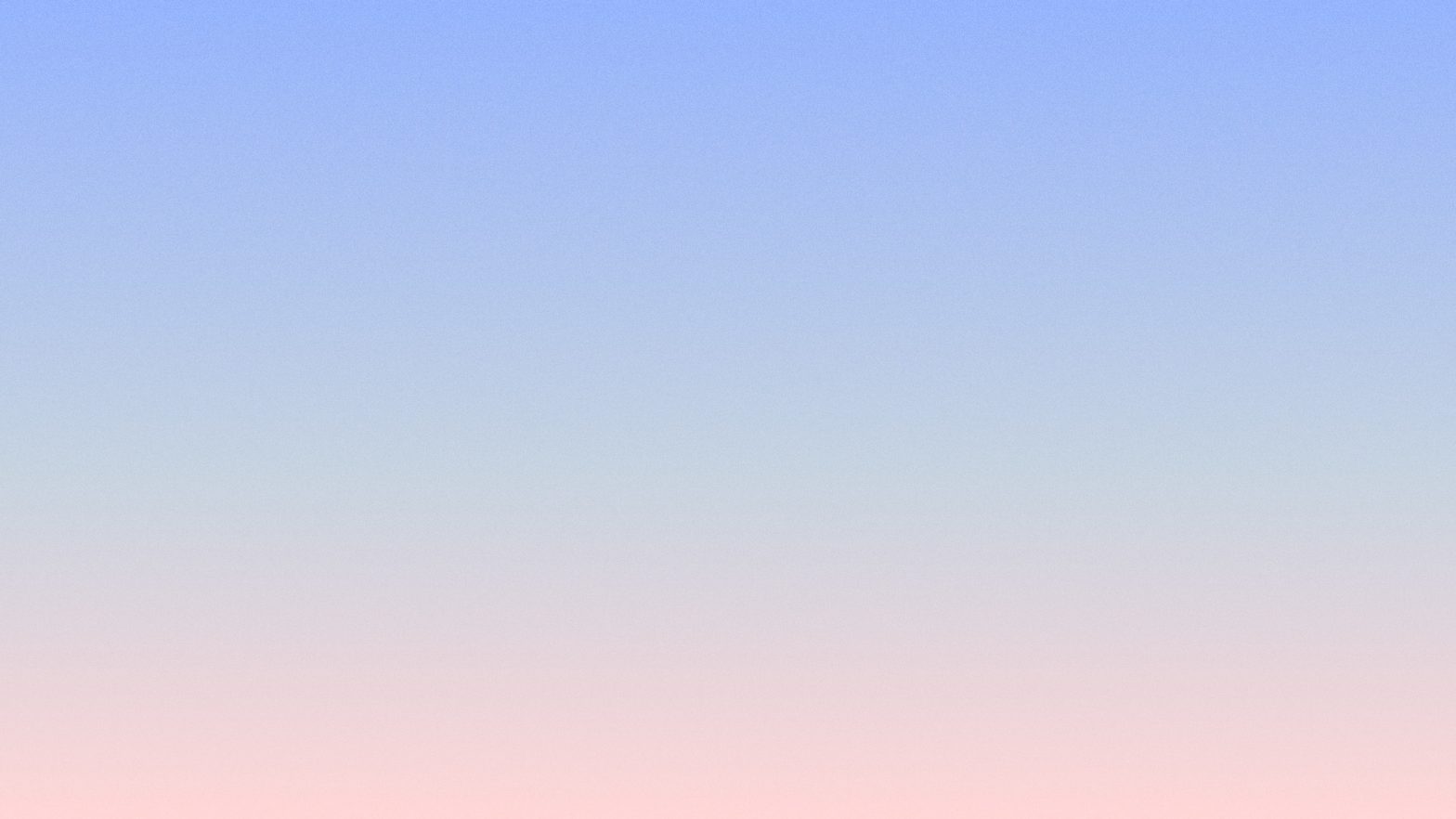’50年代の半ば、私は関西の地方都市・和歌山で大学受験を目指していた。中学校を卒業と同時に社会に出て、1年後に夜間の高校に入り、働きながらの受験勉強であった。当然、昼間に学ぶ学生にくらべるとハンディキャップがある。それをはね返すには、何としても自分の得意を見つけ、そこを、集中して磨き上げる以外にないと考えるようになっていた。
自分の得意探しを続けていたある日、部活で時折り出入りしていた美術部の部室で、「美術手帳」という美術の専門誌を見つけた。ページを捲っているうちに目に飛び込んできたのが“デザイン”という文字、当時の地方都市では、あまり耳にしない単語であった。
そこに紹介されていたのが、格好良い外国映画のポスターやアメリカの店舗のショーウインドウ、それに最新の電気製品など。それらは私の目にすこぶる新鮮で、胸ときめかすものばかりだった。デザインは面白そうだ、何だかよくわからないけど魅力的だと直覚した。自分の将来に対し、何かを求めていた私の心に響いたのである。
小学校の後半から中学の3年間を通して、図画工作では、市内や県下で賞をもらうほどのレベルにあった。とは言えもちろん我流であり、基礎を習ったわけでもない。でも、間違いなく絵を描くことが好きではあった。“デザイン”ならもしかして、自分にもできるかもしれない、自分の力を試せるかもしれない、そう思った。
このころ、京都や金澤にも美大があるのは知っていた。が、デザインを勉強するなら東京でと、そのころ知り得るわずかな情報から、自分なりにとことん考え心に決めた。
決めるということは実に難しい。その後何度かこういう場面に直面してきたが、その都度、なんとかそれらを乗り越えてきた。そうした経験を通して、“決断”とは、“断つことを決めることだ”と考えるようになった。
まず自分自身が、こうしたい、こうありたいと強く想うこと。そして、その実現のために考え出したいろんな案を、消去法で一つずつ断っていく。最後に二つか三つ残って、どうしても一つに絞れないときは、目を瞑って思い切って一つを掴みとる。そして選んだものを、後悔のないようとことんやり切る、という自分なりの方法を、苦し紛れで編み出したわけだ。
学生時代に読んだ本に、工業デザインの神様と言われているレイモンド・ローウィの著したデザイン書、「口紅から機関車まで」がある。原題が「Never leave well enough alone」で、「まぁいいか、というところで諦めるな」という意味だそうだ。就職したホンダという会社で薫陶を受けた本田宗一郎から、耳にタコができるほど聞かされた「とことんやれ」にも通じる。この二つの言葉のお蔭で、どれだけ大変な局面を乗り越えてこられたことか。
さて、この“デザイン”というカタカナ言葉、企業内デザイナーとになって初めて知ったのだが、‘50年代の初めに日本で使われ始めたものだという。私はそれから間もなくしての二十歳前に、幸運にも、そのころ最先端の“デザイン”に出会うことができたわけだ。
その“デザイン”をいち早く学び、企業の中で役立て、そうした中で自らも商品担当役員として活躍の場を得た。そして日本という国も、“デザイン”を武器に見事に戦後の復興を遂げ、世界が羨む豊かな国に成長した。“デザイン”の果たした役割は大きいと言って過言ではない。
が、確かに、日本は物質的に豊かになったものの、‘90年代初頭のバブル経済崩壊で挫折し、自信を喪失し、そして停滞した。“デザイン”は、物質的豊かさの追及から精神的豊かさ、言い換えれば“成熟”の実現へと、力の発揮する向きを変えていかなければならない。そこにこそ、デザインの真の役割があると私は確信している。
“デザイン”は、デザイナーという専門家がやるものと思われがちである。私は企業での36年間、その後10年間の母校での後進の指導にと、様々な立場でデザインに関わってきた経験を通じ、生活者すべてが優れたデザイナーであるべき、という考え方を強く持つようになった。
私を含め、生活者の一人ひとりが“デザインこころ(マインド)”を昴かめ、自分自身を、自分の身の回りを、そして家庭をデザインし、そうした“デザインちから(パワー)”が束なることによって、成熟した美しい日本を創り上げられるのではないかと、このところ、つとに思うようになった。