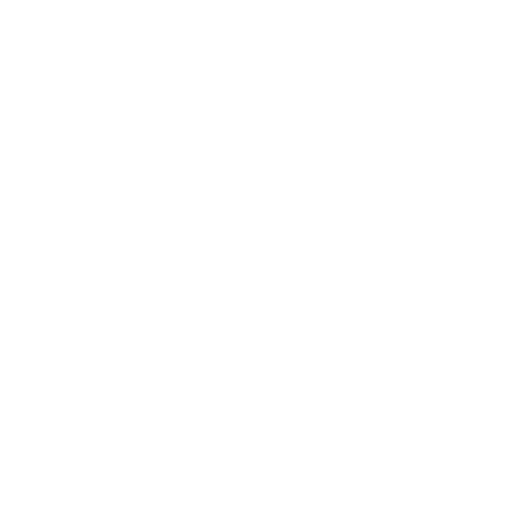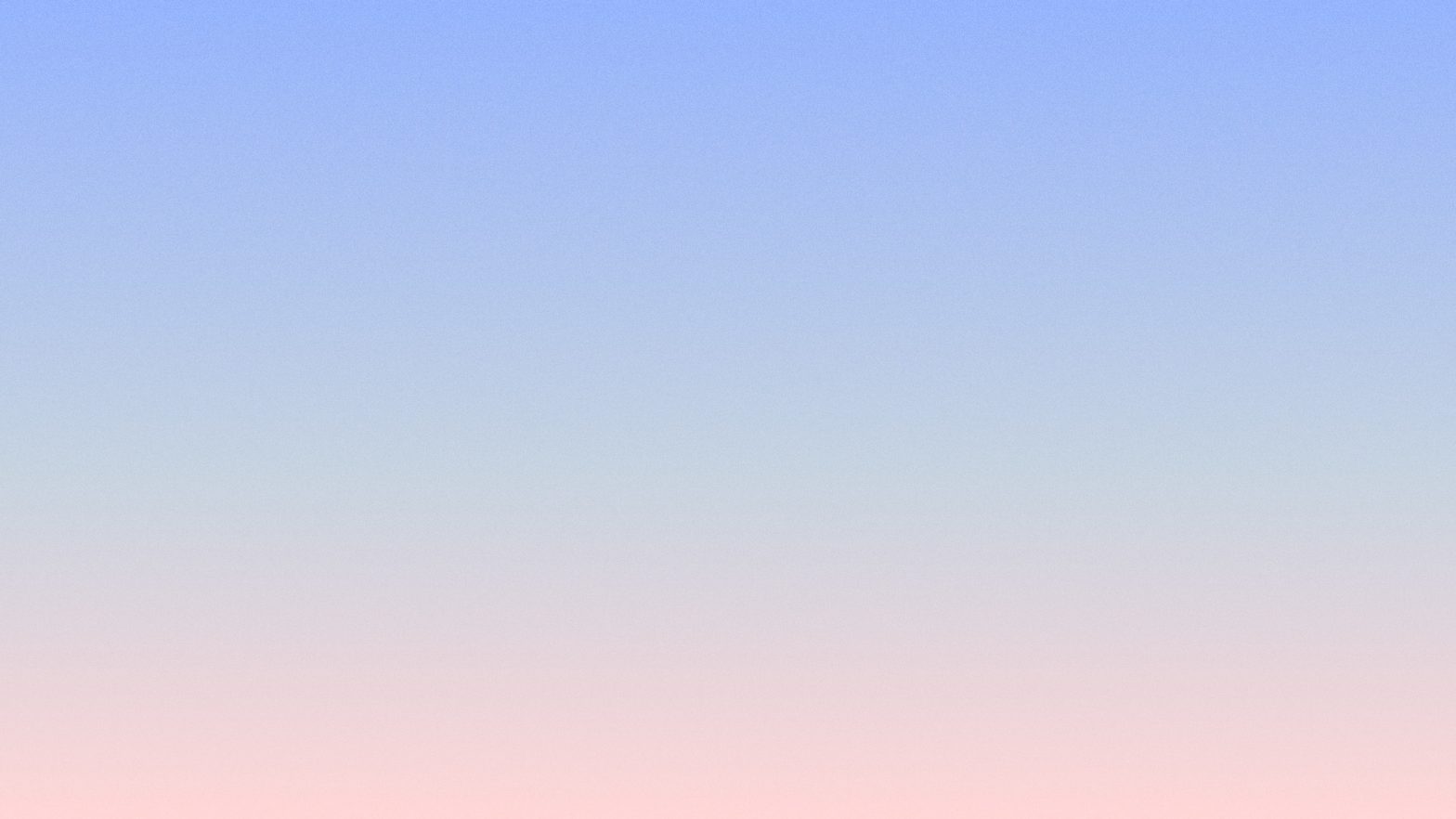我が家には鏡が多い。それも、ほとんどが姿見ぐらいの大きさで、壁面という壁面、至るとことに張り付けてある。もともとは、狭いマンションを広く見せるための工夫で、リビングなどの壁に貼り付けたものが、そのうちに、玄関にも寝室にもという具合に広がっていった。訪れた友人たちからは、“鏡の家”などと揶揄されたものだ。
私は出勤で家を出る前、玄関で、必ず一度は壁の姿見と対峙するようにしてきた。頭のてっぺんから足の先まで、髪の整い具合や顔色に顔つき、もちろん服装から靴に至るまで、ざっと眺めてみる。一番気にするのは、元気そうに見えるかどうかということ。前の日に飲みすぎたり、調べ事があって夜更かししたり、悩みごとがあって寝られなかったりが、顔に出てしまっていないかどうか、などという具合にである。
生身の人間である以上、常に元気でいられるわけではない。出かけに鏡を見て元気そうに見えないときは、ネクタイを変えたりジャケットを変えたり、場合によってはシャツまで変えることもあった。先に、“顔に出る”の喩えから牽いて心の持ち方の大事さを述べたが、それでも足りない場合は、このようにして、人から元気そうに見られるよう心掛けてきた。
本田技研の役員になったとき、先輩役員に尋ねたことがある。「毎日の服装は、どのように決めておられるのですか」と。先輩の言うには、前夜に、奥さんが枕元に、翌朝に着るスーツやワイシャツ、ネクタイ、靴下と、ワンセット揃えて用意してくれるのだそうだ。スーツを決めると、他のものはほとんど自動的に決まるので悩まないで済むとのこと。朝の出掛けの慌ただしいなか、すこぶる助かっているのだと言う。
しばらくは教えられたようにやっていたが、どうも自分には馴染まなかった。それまでの仕事場である研究所では、全員が白いユニフォームに着替えることになっていて、車通勤ということもあってどんな身なりでも良かった。
そんなわけで、上下揃いのスーツの持ち合わせもなく、当時流行りのアイビー調のジャケット一着というありさま。そのくせ、ラフなシャツやズボンをとっかえひっかえ、自分なりのファッションを楽しんでいた。そうしたことが、まるでなくなってしまったのだ。
どうして“元気”を大事にしようと思ったかというと、先にも述べたが、バブル経済崩壊後の苦しいなかで暗い顔をして仕事をしていたとき、当時の社長から、「そんな暗い顔をしていたら、つくっている商品まで暗くなるぞ」と言われたことから始まっている。毎朝、元気良く出勤し、みんなで顔を合わせ、明るく挨拶を交わし語たり会う。そして、その日一日が始まるというわけだ。
前の晩のうち家内に、次の日に着ていくものをワンセット揃えておいてもらうというのは、確かに安心であり実に楽ではあるが、自分であれやこれやと考えてみることで、「よし、今日は頑張るぞ!」という気分が盛り上がってくる。
そのころの先輩役員方は、上下揃いのダークスーツが相場となっていた。しばらくはそれに倣っていたものの、ネクタイとワイシャツぐらいしか選択肢がなく、就任祝いで買ってもらった2着のスーツでは、どうにもならなかった。
イギリスへの出張の際、思い切ってちょいと上等なカシミヤのジャケットを買った。その後これが思いのほか重宝し、仕事着としていろんなバリエーションが楽しめた。さすがにノーネクタイは憚られたが、それでも先輩役員からは、「ジャケット出勤は本田さん並みだね」と冷やかされたりもした。そしてその頃から、他の役員の、ジャケットでの出勤が増えてきたようだった。
限られた衣服ではあるが、コーディネートを工夫しているうちに、周りから「おしゃれしてますね」、などと言われるように。が、その反面、「外見を気にする人みたい」、との陰口も聞こえるように。ということは、「元気に見えるように」、との意思をもってやっていることが、良きにつけ悪しきにつけ、周囲の人に伝わったということである。
結局、鏡と対峙するこうした日々の繰り返しが、自分を磨くという意識を高めることになった。日本には、「身だしなみ」という言葉がある。身の回りについての心掛けということなのだが、これは単に見え方というだけでなく、趣味や嗜好、言葉遣いや教養に至るまで、その人の人となりを測る言葉でもある。私はこの言葉を、自分をデザインするための「物差し」にしている。