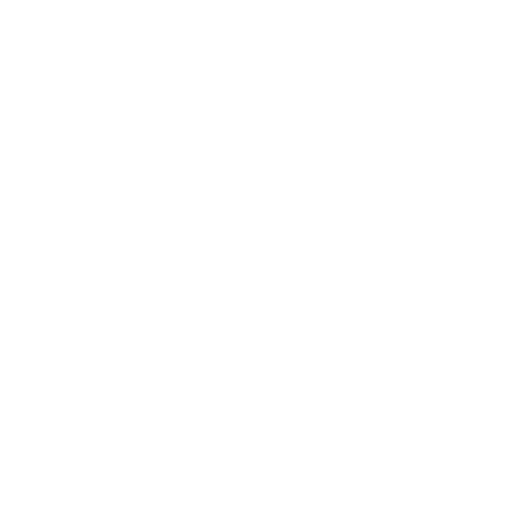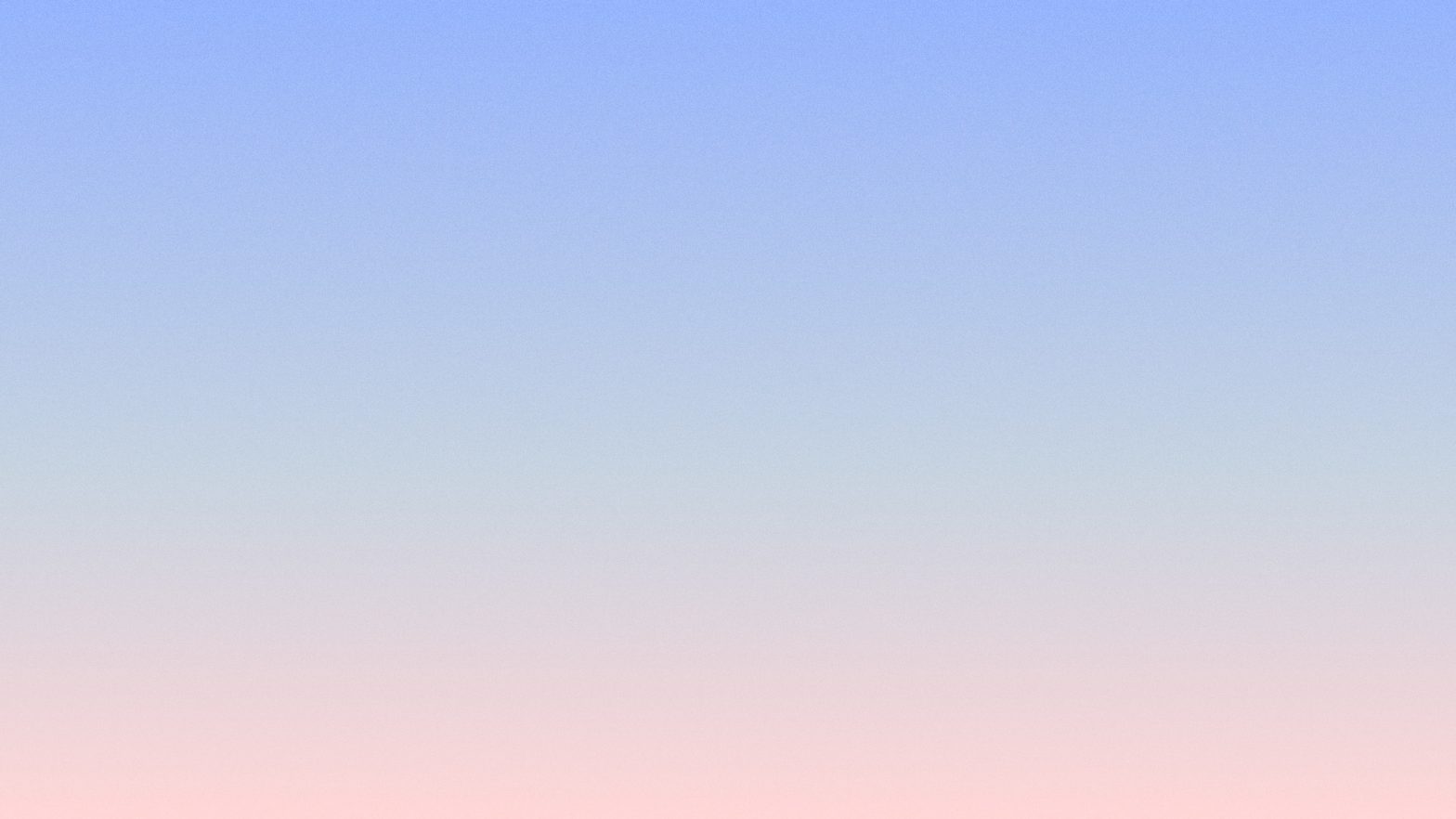ホンダに入社以来ずっと、様々な新車開発に携わってきた。その中にはヒット作もあるがそうでなかったものも少なくない。そして面白いことに、うまく行ったり行かなかったりの波を、ほぼ10年の周期で繰り返してきた。注目すべきことにこの3つの波には、それぞれにピークというか「山」をつくるきっかけとなる車が登場する。
最初の「山」をつくるきっかけとなったのは1972年発売の初代「ホンダシビック」で、私が30代に入ったばかりのころ。次が1983年発売の2代目「ホンダプレリュード」で、これは40歳のはじめ。3回目が1994年発売の初代「ホンダオデッセイ」で、50代前半ということになる。
という訳でだいたい10年ごとになるが、驚くことにこの3つの車のコンセプトやデザインは、大ヒット商品という点では共通しているものの、時代性というかそれぞれにおよそ違う。
「山」の前はいずれの場合も「谷」、まさしく「どん底」の状態であった。初代シビックの直前は4輪から撤退しようかとさえトップは思っていたと聞く。プレリュードの直前は、「ホンダらしさ」すなわち企業の存在にとって最も大事な「アイデンティティ」が無くなったと言われた。オデッセイの直前は、「赤字転落か、M社と合併か、ホンダどうした」と。
結局、これら「どん底」に共通していたのは、身のすくむような危機感だけがあって、お金、人手、時間の何もかもがなかった。が、こうした「どん底」の中でつくった車には学ぶべきところが多い。
一例だが、1960年代の終りのころ、初代シビックの開発にあたり研究所所長から、「すぐ、鈴鹿工場のラインを見てこい」と言われ勇んで出かけていった。が、長い組立ラインに、我々が鼻高々でつくった「ホンダH1300セダン」がポツンポツンとしか流れていない。
「閑古鳥」が鳴くとはまさしくこのことでさすがに青くなった。この光景を「見てこい」と言われたのだ。その後、検討チームが編成された。大ショックを受けて帰ってきた連中が、それでも、お互いの夢を侃々諤々、喧々囂々、夜を徹して何日も激論を重ねた。
こうした逆境の中で、それを逆手にとった一口言葉がいくつも生まれた。たとえば、どんな車にしようかという議論の中で、最初にできたのが「都市交通のモビリティ」。が、ホンダらしくないと上司に一蹴され、「小さくて、いばれる車」が生まれた。「小さいんじゃ、いばれないね」と言われ、考えた末、ナナハン(CB750)と並んでも、ひけをとらないモンキーホンダやダックスホンダを引き合いに出して説明した。
短い全長で、どうしても流れるようなシルエットはつくれず、それを逆手に、見るからに安定感があって地面に吸い付くような、「台形スタイルの安定感」という外観イメージが誕生する。「キビキビとした走り」というのもあった。
さらにまた、「この車のイメージは、アラン・ドロンではなくて、チャールス・ブロンソンです」「白魚の手ではなくて、げんこつの手ですよ」というのも。そして、コストがかけられず機能部分しか付いていないインテリアを、「シンプルbutチャーミング」と呼んだ。
それに基本コンセプトを「ユーティリティ・ミニマム」「ベーシック・カー」とするなど、こうした一口言葉は、私をはじめデザイナーたちがつくり出していった。そして「都市交通のモビリティ」に因み、北米セールスの責任者の発案で「CIVIC」という名称がつけられた。
初代シビックは、日本で初めてプロジェクト制を導入して開発された車と言われている。研究所には、艤装、ボディ、足回り、デザイン、エンジン、走行テスト、材料テストなどの専門部署があり、それこそ我こそはと思っている一騎当千の連中が数名、選ばれ集められた。それだけに、自己主張も強い。
最初のうちは、それぞれが専門知識をひけらかし、かくあるべしとの理想論を振りかざし、なかなか意見がまとまらない状態が続く。が、そのうち、「じゃあ、一口に言ってどんな車を創りたいんだよ」という一人の投げかけから、議論に方向性が見えはじめた。
様々な意見をまとめみんなが共有できる短い言葉を創る能力は、家庭でも、いろんなサークル活動でも、それらのチームやグループの人たちが、心を一つにして目標に向かうためには、どうしても欠かせないものとなる。
初代シビックの開発後、当時の社長久米是志は、「既成概念を打ち破るような創造のエネルギーは、共通の目的を持った異質な人々が集まって、対等な仲間意識で、明るく事に当たることにより生まれる」として今に伝えている。こうした考えを推し進めるために、「一口言葉」が果たした役割は大きい。