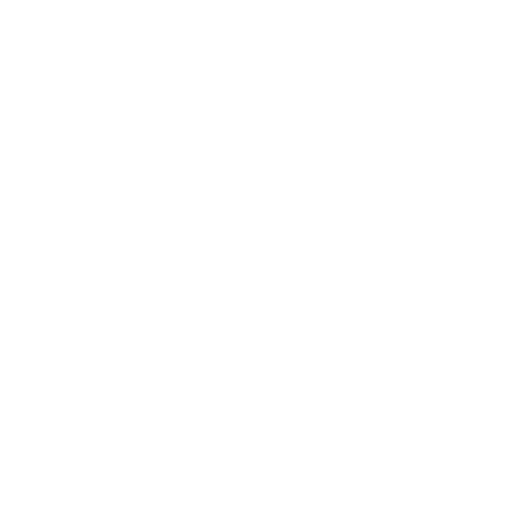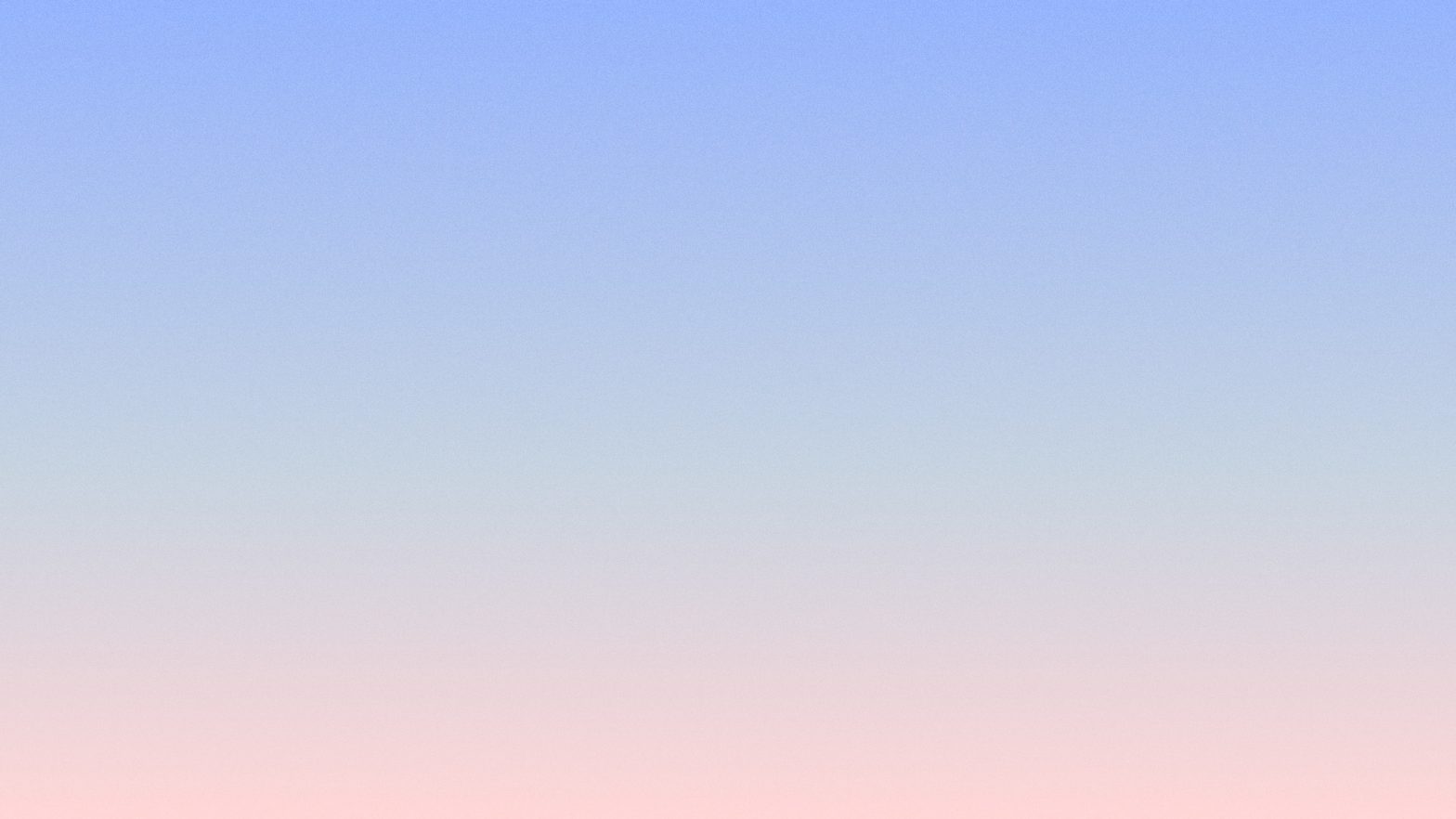終戦の翌年のこと。小学校に入る前の面談で、先生が、「ここに自分の名前をひらがなで書いてみて」と。ずいぶんと前もって練習をしてきたので、自信をもって思いっきり大きな字を書いた。「きみは左ギッチョかね」といきなりである。
母に代って付き添っていた祖母は、「そうなんです」と恥ずかしそうに。さらに「で、ごはんのときもそうかい」と聞かれ、「はい…」と祖母はうな垂れた。「まあいいでしょう。元気な字だから」ということで、無事に入学が認められた。ほっとした気持ちで家路についた。
が、その夜、母は祖母から「あんたの躾が悪いから」とこっぴどく叱られていた。母はそのころ、父の戦死で悲嘆に暮れながらも、残された呉服屋と言っても建物疎開で店もなく周辺は焼け野原の中、お店の再開に向けとびまわっていた。子供心に、母には心配を掛けないよう頑張っていたのだが……
「よろしくお願いします」と、母は私を祖母に委ねた。その夜から私は、字を書くのもごはんを食べるのも右手になった。とは言え、祖母のいないときは、何をするのもすぐに左手に戻っていた。
この秋、喜寿を迎えた。そんな私が、箸の正しい使い方に目覚めたのは古希も近いころ。家内からは結婚以来ずっと、あなたの箸づかいはみっともないと言われてきた。左利きを言い訳にするとその都度、「貴方は、絵も字も右手で上手にやれるじゃないの」と。
娘たちに厳しく箸づかいを教えているのを眺めながら、あのとき祖母に逆らわずしっかりと習っておけばよかったのに、と悔しい思いをしていた。娘たちが「お父さんだって」と、家内に逆らっているのを耳にするのが辛かった。
箸の正しいもち方は、一本を鉛筆で字を書くようにもち、もう一本を親指の付け根の方から差し込んで箸先を揃える。こちらは動かさずに、鉛筆をもつような方を動かして先を開いたり閉じたりする。
70の手習いで、皿に載せた100粒ほど小豆をもう一つの皿に一粒ずつ移す。この単純な作業を朝食前に半年ほど続けたところ、「何とか見られるようになったわね」と家内に。あれから7年が経つ。桃栗三年柿八年というが、この頃やっと箸が仕事をするようになった。
古事記に「箸」のことが出てくる。竹でできた火箸のようなものだったと。神代の昔には漢字はまだなかったろうが、「はし」という日本語はあったはずだ。広辞苑によると「はし」には、箸、橋、階、嘴、梯、端などの漢字が当てられている。
嘴(くちばし)説など諸説はあるが、私は最近、「箸」は、手の「端(はし)」のことを言ったのではと思うようになった。手の先端、すなわち指先代わりに使えるモノを指したのではないかと。
このように考えると箸の最終的役割は、手(身体)と一体となり思った通りに動くことにある。身を美しくと書いて”躾“という。だから箸の動きも当然、身の内として美しくなければならない。
古今東西、世の女性の関心は指先の爪に向けられてきたようだ。磨いたり色を塗ったり飾りをつけたりと。最近はネイルアート、昭和の時代はマニキュア、過去を辿るとエジプト時代の女王や江戸時代の遊女と、そのエピソードを語るにことをかかない。男性の目から見ると、ことに老来の身ともなれば、爪の美しさは桜貝のような素の美しさが良い。
そして指先は白魚のような手が目に優しい。さらには、家内はこういうことを承知で、娘たちに箸の使い方を教えていたのだろう。美しい日本の箸文化を伝えるのはやはり女性なのかと、また悔しがった。そして、時折やってくる孫娘の箸づかいもまた、実に美しいのだ。
箸は、日本人が石器時代以降に、火を使うようになってはじめて手にした道具である。一本の竹か木を、Uの字に曲げて使うか2本にして使うかはともかく、人が生きるために、現在に至るまで時代を超えて使い続けてきた、極めてシンプルで、かつ最も有益な道具と言っていいだろう。
古来、日本では、仕草、立ち居振る舞い、佇まい、という動作のあり方を大切にしてきた。いわゆる行儀作法である。庶民の間では{躾(しつけ)と称して、子供が物心のつく頃から、親が生活の中での所作について、口うるさく言って身体に叩き込む。
躾ができていないで大人になると、「親の顔が見たいものだ」と蔑まれる。思うに躾は、個をデザインするための基本ということだ。箸の使い方(仕草)は、その端緒と言えるのではあるまいか。