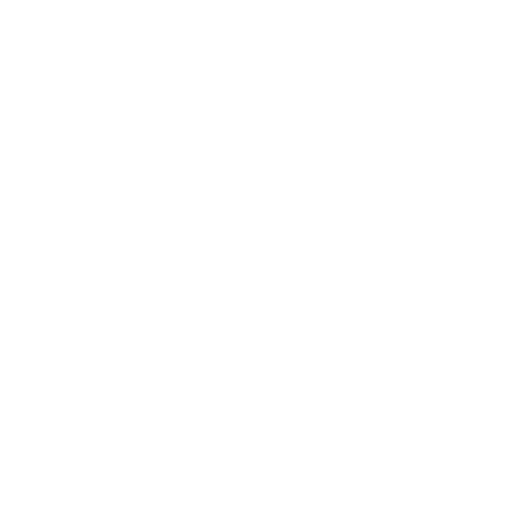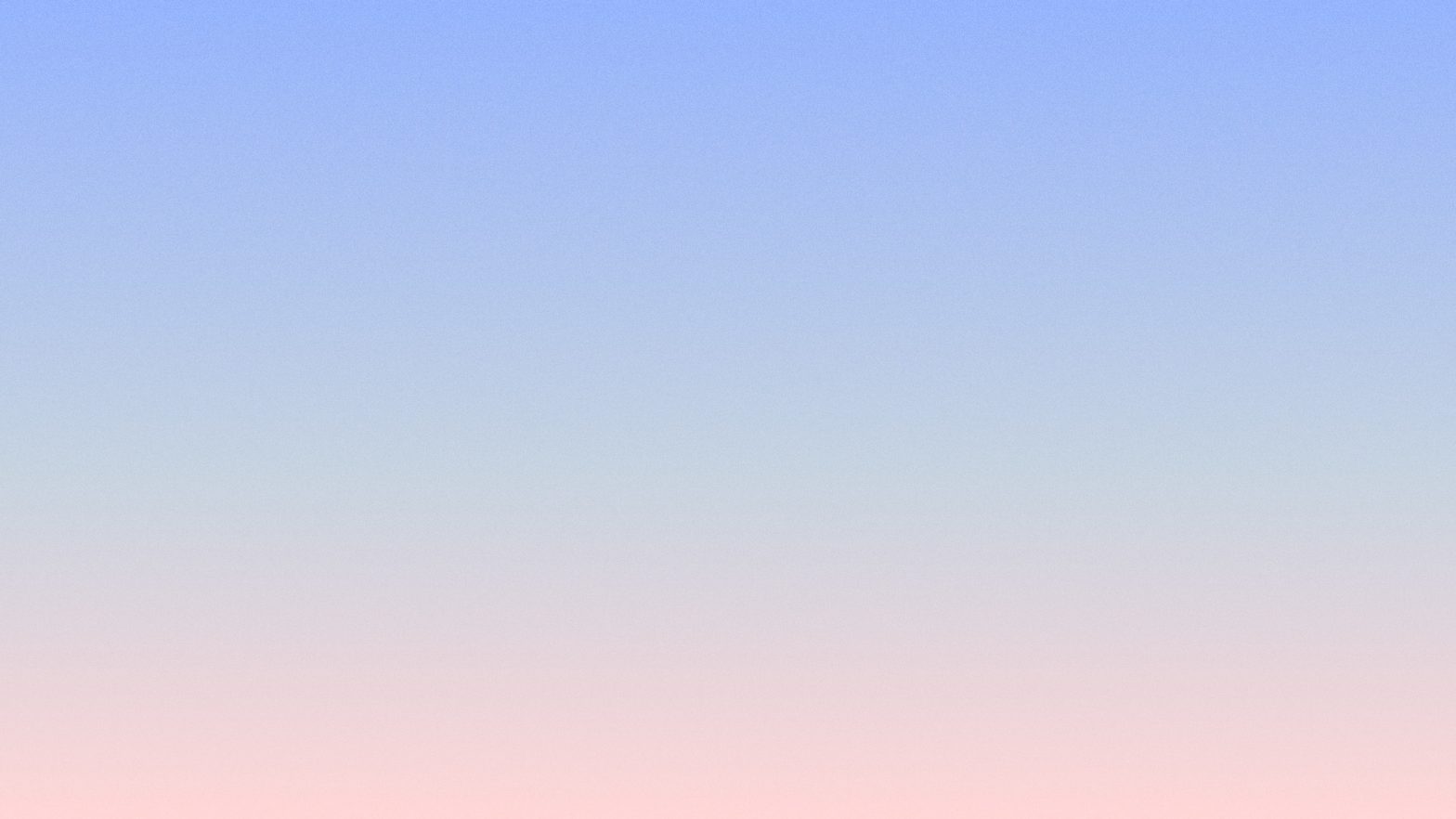何か、「モノ」の形を描こうとするとき、どういう手順で行うのだろうか。まず、白い紙を用意し鉛筆を持つ。次に、頭の中に浮かんでいるイメージのどこから描き始めるかを決める。最初に紙と鉛筆が接触する点が、それである。その「点」を始まりとして鉛筆を移動させると、「線」が描ける。それが「モノ」の輪郭となってゆく。
対象が立方体のように特殊なものであれば、輪郭は直線だけで描き表せるが、この世の中のほとんどの「モノ」は、曲線の組み合わせが必要になる。人工のものならともかく、直線だけで描き表せる自然の「モノ」は、まずない。
初めてクレヨンを持った小さな子供も、アルタミラの壁画も、輪郭を描いてモノの形を表わそうとしているから、こうしたやり方が人間にとって、最も基本的なモノの描き方なのであろう。が、輪郭が全部描けたとしても、立体が表現できたとは言えない。何故なら、立体は「面」で構成されているからだ。
何とかして、「面」を描き表わさなければならないのだが、これを鉛筆の「線」だけで行うことは、かなり難しい。紙の上の「線」は、輪郭や立体の折れ目や色の境目を、かろうじて表わすことができるにすぎないからだ。
「面」は、「点」が移動して「線」が生まれるがごとく、「線」が移動して生まれるのである。だから、無数に線を並べて描けば「面」が表現できる理屈だが、紙の上で単純にこれをやると、まっ黒になるだけで訳が分からなくなる。
我々は、点から線さらに面を描く、という手順を経て「形」を表現しようとしているのだ。点は「存在」のみを表すが、線はそれに「流れ」が加わる。面は広がりを持ち、さらに明るさの変化を伴っている。紙の上に鉛筆で面を表現するには、この明るさの変化を利用する。具体的には、並べた鉛筆の線の粗密、あるいは、塗りつぶした濃さの違いによって明るさの変化を表す。
このとき、紙の白さ以上の明るさは表現できないわけだから、これを最も明るい部分とし、鉛筆でべったり塗りつぶした部分を最も暗い部分として、その間の何段階かのグレーのトーンを描いていく。そして、この作業を終えてはじめて、「形」が描き表わせたことになる。
「姿・形(すがたかたち)」とよく言われるが、私は勝手に、「姿」の方が、より上位の概念であると決めている。様々なモノについて、形が整っているとか、美しい形だとか言われることがある。これらは外形を評価した言い方だが、人によって評価の基準はまちまちで、形どうしを比較しても、どちらが美しいのか整っているのか、本当のところはよく分からない。私が、これらよりも「姿」を上位にしたのは、それが、「形」と人の「心」との関わりを、表わしたものであると解釈しているからだ。
あるプロダクト(製品)がお客さんから、「親しみやすそう」、「丈夫そう」と評価された。デザイナーがそうした意図を持ってデザインし、その結果にお客さんがそのとおりの反応を示したということだ。製品が本来、「親しみやすそう」「丈夫そう」なのではなくて、そのようにデザインされたからである。
「どうです。親しみやすい形でしょう」、「おお、なんと親しみやすい形なんだろう」と、デザイナーとお客さんは製品を介してコミュニケーションしているわけだ。このようなつくり手の気持ちや考え方、それに心が読み取れるような「モノ」に備わっているのは、「形」ではなくて「姿」なのだと私は思っている。
「認知心理学」という、人の心の仕組みを研究する学問がある。脳のメカニズムと人の精神がどのように関連しているか、つまり、「脳の原理」を明らかにしようとするものだ。認知心理学には、「階層性」という考え方がある。これは人が認識したものを、心の中のイメージとして構築する場合、単純なものからより複雑なものへと、段階をふんで構築していく性質のことだ。
この認識は部分から全体へ、点・線・面というような順に行われ、一旦認識された後、人は、単純なものから順に刺激を受けなくなっていく。これが、「飽きる」という状態であるが、人がそれらに何らかの意味を感じている場合、つまりそれが、先述の「形」ではなく「姿」であるなら飽きることはない、というのが私の説である。
この世のすべての「モノ」は「形」を持っているが、そのような「モノ」に人の心が働き、手が加わることによってはじめて、「姿」が備わるのではあるまいか。