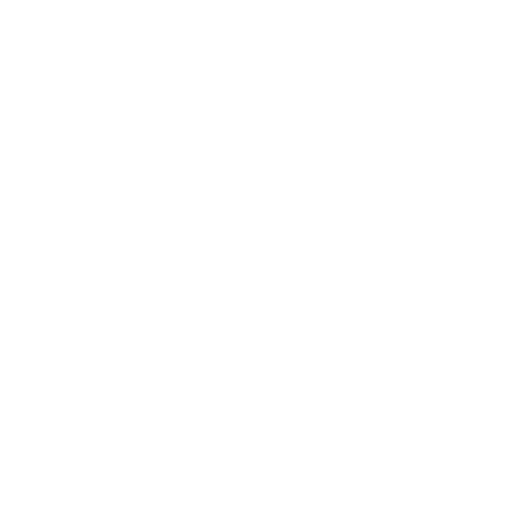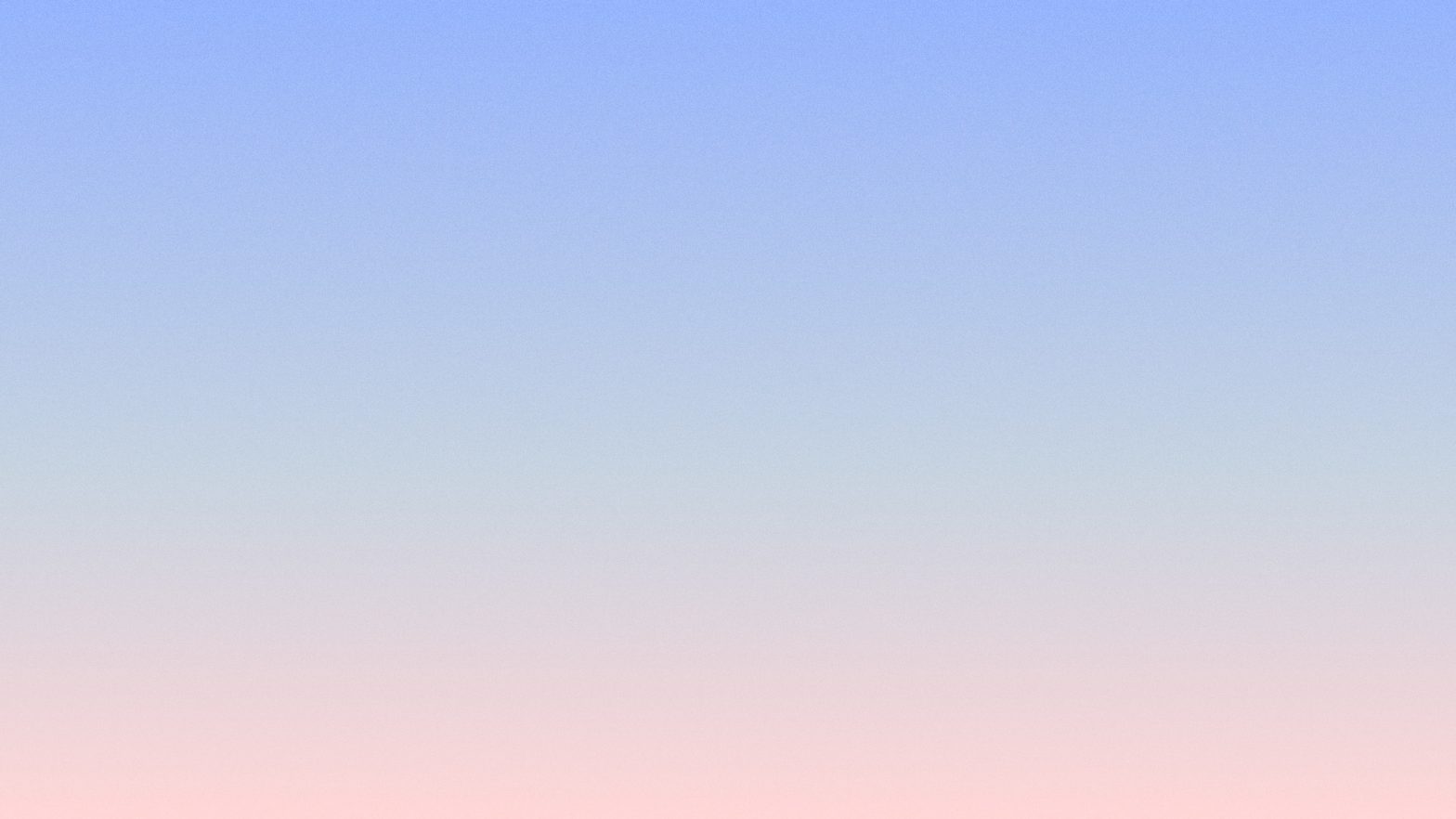「おにぎり」に付きものは、「漬けもの」である。今では漬けものは買ってくるものになってしまったが、私たちが子供のころは、それぞれの家庭で漬けるものと相場が決まっていた。
たとえば糠(ぬか)漬けは、木製の樽や桶に糠床(米糠を水で練り、塩やそのほかの調味料を加えたもので、各家庭独自の味がある)を入れ、そのなかに大根や茄子など野菜を埋め込み、ふたをしてその上から「漬けもの石」を乗せて何日間か置く。そうすると、大根や茄子の水分が糠床の塩分と入れ替わり食べごろになる、という大変に手間ひまのかかるものである。
さて、この「漬けもの石」、もとはと言えば、河原に転がっているようなただの石ころである。しかしこの「漬けもの石」は、漬け物を漬けるための重要な「道具」の一つなのだ。
小学生のころ、おばあちゃんから、「信弥、石、拾ろてきてくれへんか」、と頼まれた。「なんに使うねん」、「漬けもん石や」ということで、紀ノ川の河原に、自転車に乗って、「漬けもの石」になる石を拾いに行ったことが思い出される。
ただの石ころを「漬けもの石」と呼ぶからには、他の石とは違う何か特徴がありそうだ。それにはまず、漬けものの重石(おもし)になる適当な大きさと重さであること。それから、転がりにくく、手で持ちやすい形であること。さらには、固くて割れたり崩れたりしないこと。デコボコだったり尖っていたりしないこと。などに加えて、漬けものという食べものに関わるのだから、それなりの清潔な「見た目」も大切になる。
河原に行くと、当然のことながら石ころだらけである。どれにすべきか,思案にくれた。そこで、おばあちゃんの体の大きさや力の強さ、持ち上げたち下げたりする姿を思い浮かべながら、おばあちゃんのつもりになって持ち上げてみる。どれにしたら喜ばれるのか、おばあちゃんの嬉しそうな顔を思い浮かべながら、こうした条件に合った石を探した。
石を持ち帰っておばあちゃんに見せた。「信弥、これ、ちょうどええわ」、「ようみつけたなあ」と褒めてくれた。嬉しかった。石は、台所の井戸端に置かれた樽の上に鎮座した。それからあと、おばあちゃんがどのように石を使うのか、重すぎはしなかったか、心配で、そっと物蔭から見るようになった。
ある日、近所のひとが遊びに来て、その漬けもの石を見て、「ええなあ、よう似おてるわ」と。おばあちゃんは、「信弥が拾ろて来てくれたんや、ええやろ」と自慢げに言った。あとになって、その石が、樽にも台所にもおばあちゃんの好みにも合っていることを褒めてくれたんだよと、自ら解説してくれた。
これは、デザインをするプロセスや行為と全く同じである、と言ってよい。スーパーなどで売っている成形品の「漬けもの石もどき」のように、今は全ての「モノ」が「商品」として扱われてしまう。そして「デザイン」は「モノ」と関わるのだから、デザインが扱うのは「商品」であると言える。特につくり手、企業から見た「デザイン」というのは、「商品つくり」の一環にほかならない。
使い手にとって、日常の暮らしに必要なさまざまなモノを選択するとき、河原の石ころをそれぞれの基準で選び、「漬けもの石」に進化させるように、たくさんの「モノ」の中から本当に必要で暮らしに役立つもの、自分の手足となるものを選択することも、広い意味でのデザインであり、使い手にとってのデザインなのである。
お母さんのおにぎり、おばあちゃんの漬けもの石、二人とも立派なデザイナーであり、おにぎり、漬けもの石、ともに素晴らしい成果物と言える。片やモノづくり、片や在りもの利用と、いずれもデザイン的であり、工夫の所産でもある。日常生活には、この二人のような場面に遭遇することがままある。そんなとき、デザインという考え方を意識して対象に立ち向うかによって、暮らしようが変わってくるはずだ。
私の家内は、お母さんのおにぎり、おばあちゃんの漬けもの石、両方を備えている。その上、私をデザインする達人でもある。デザインを職業としている私が一目置いているのは、対象物をよく観察し、いつもそれがどうしたらもっと良くなるかを考えているところである。その創意工夫のお陰で、今の私があると言っても過言ではない。私が大学で教鞭を執っているとき、女子学生に、「早く結婚して、旦那さんのデザインをした方が面白いぞ」、などと言っては煙たがられていた。