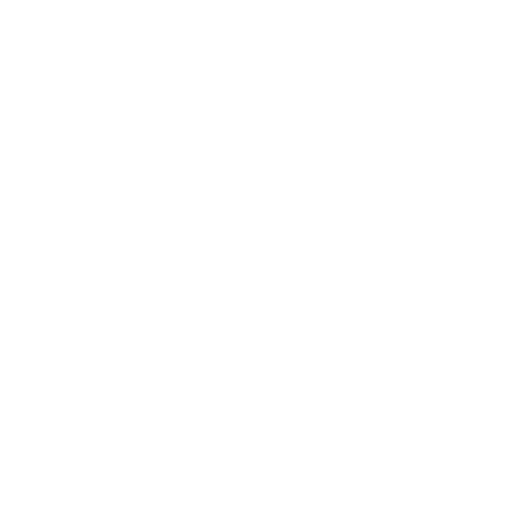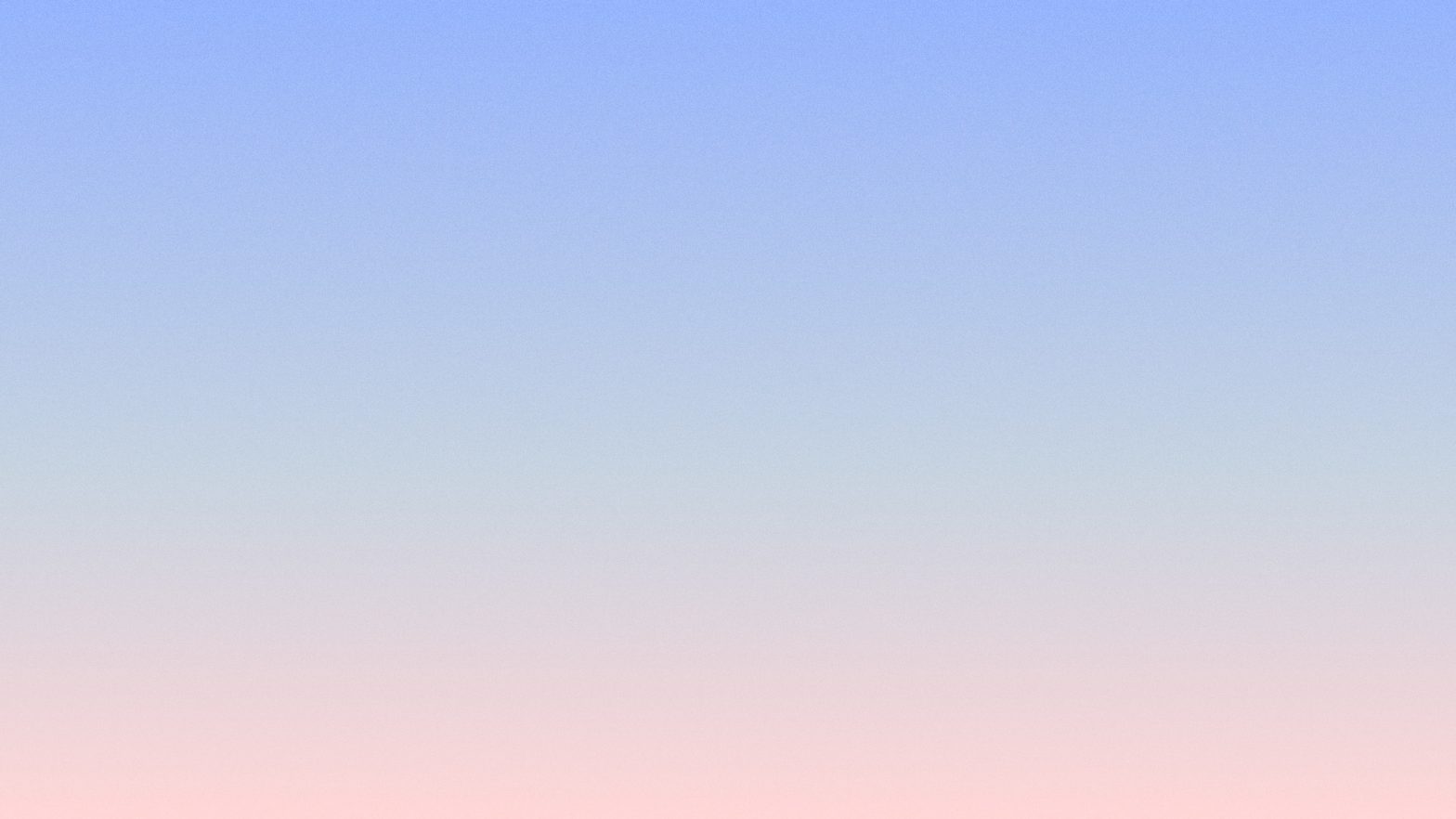20代後半、入社からまだ3年ほどのころである。本田宗一郎さんが4輪走行テスト室で、「これをデザインした者をここへ呼べ」と言って怒っているとの伝令。室長も上司も見当たらず、思い切って担当の自分が行くしかないと。いきなり「これをやったのは、君か!」。訳が分からないまま、「ハイ」と答えたが後の祭り。
「ホンダN360」の試作車が置いてある。「どうして、こんなに背が高いんだ」と厳しい目。見ると確かに、デザイン室で見るクレーモデルよりどう見ても背が高い。と言うか、ボディ(車体)が車輪から浮き上がっているように見えた。しかも、後部が上がって前につんのめっている。咄嗟に、タイヤとボディの繋ぎ方に問題があるなと。
「サスペンション(懸架装置)のせいでしょうか」と答えると、「君は、ずっと見ていたんだろうに」と、ますます声が大きく。「いえ、はじめてです」と答えようするその前に本田さんは、「すぐ、直しなさい」と言って行かれた。
私は気が動転して、何をどう叱られたのかよく分からなかった。そばで見ていた担当者が言うには、本田さんが来られていきなり、「格好悪い。デザイナーを呼べ」になってしまったという。こんなことで叱られるのはいい迷惑だと思ったが、以来、試作車は真剣に見なければと心に決めた。
車のボディは、ぐにゃぐにゃで不確かなサスペンションを介してタイヤの上に乗っかっているもの。頭では分かっていたが、その時はじめて、こう言うことかと思い知らされた。デザイン室のモデルをあらためて眺めてみると、つくり勝手で水平に置かれてはいるが、どういう水平(高さの設定)なのか、答えられる人間は誰もいなかった。
そんな訳だから、設計との取り決めも約束事もきちっとしたものがなく、お互い好き勝手にやっていたというのが実情で、設計の人たちもあわてて問題の試作車を見に行ったという。そこで彼らも、「それにしても、これは格好悪いね」とびっくり。お互いに相談しながらやって行こうという話になった。
その後、「格好いい位置」にボディを納めるのに、設計の人たちはずいぶん苦労したと聞く。この経験から私は、「自分でやったものは、自分の目で確かめる」ということの大切さを学び、ことにデザイナーは、「目が命」であると思い知った。「みる」も色々だ。目で見る、身体で視る、心で観る、身体を看る、心を診る。やはり最後は、「心眼」にまで行き着くのだろう。
もう一つ、30代半ばのこと。「人間のように、気配を感じる車ができないかねぇ」と本田さん。人は雑踏の中で、他人とぶつからずにスイスイと歩ける。前方はもちろん、横や後ろから近づく人まで上手くかわしていく。こんなことが車同士で実現できるのか。開発チームの誰もが、これは極めて高いハードルだと感じた。
人間は、「五感」をフルに使って歩く。いわゆる、「視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚」によって周りの状況を感じ取る。今ならセンサーを使うことになろうが、この時代、「三等機械」を自認する自動車には望むべくもない。
そこで、運転する人の5感を妨げないためには、という身近なところから取りかかることに。「判断」や「指令」についても研究する必要があった。が、残念ながら、これらに関する専門家は所内で見当たらず、手分けをして専門の先生方の教えを請うた。
勉強の結果、一番の頼りは「目」であると。先生の話では、情報の8割は目が受け持っているとのこと。が、その目も、スピードを上げると極端に視力が落ち、視野が狭くなるそうだ。また高齢化や長時間運転も、目への影響は大きいという。いかに目を働き易くするか、目の負担を軽くするかが「鍵」となる。運転者の死角を極力なくすことに焦点を絞った。
また、メーター類からの情報はできるだけ見やすく、優先順位を付けて配置。操作類も視線を動かさずに済むよう手元に近づけ、動きもスムーズになる機構とし、視覚により得られた情報を正確に「認識」できるよう工夫した。
同時に、認識した情報を、瞬時に「判断」し行動に移せるよう「指令」するには、常に身心を正常に保たねばならない。それには「疲れない」車にすることが一番だと考えた。この研究成果で生まれたのが、1976年に発売された初代アコード3ドアハッチバック。ピラーが細く窓の大きい、“ガラスのお化け”と揶揄されるくらい視界のいい車だった。結局、人も車も同じということだ。