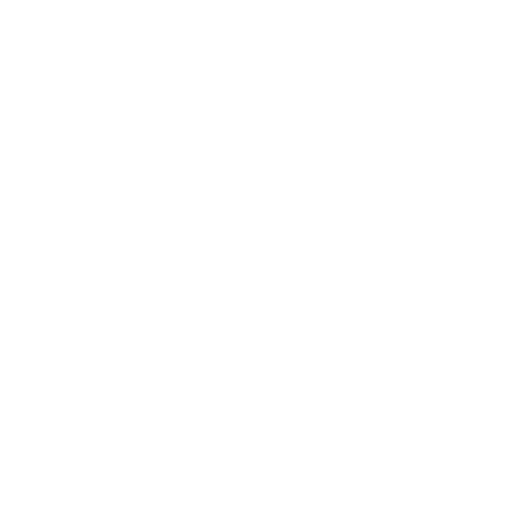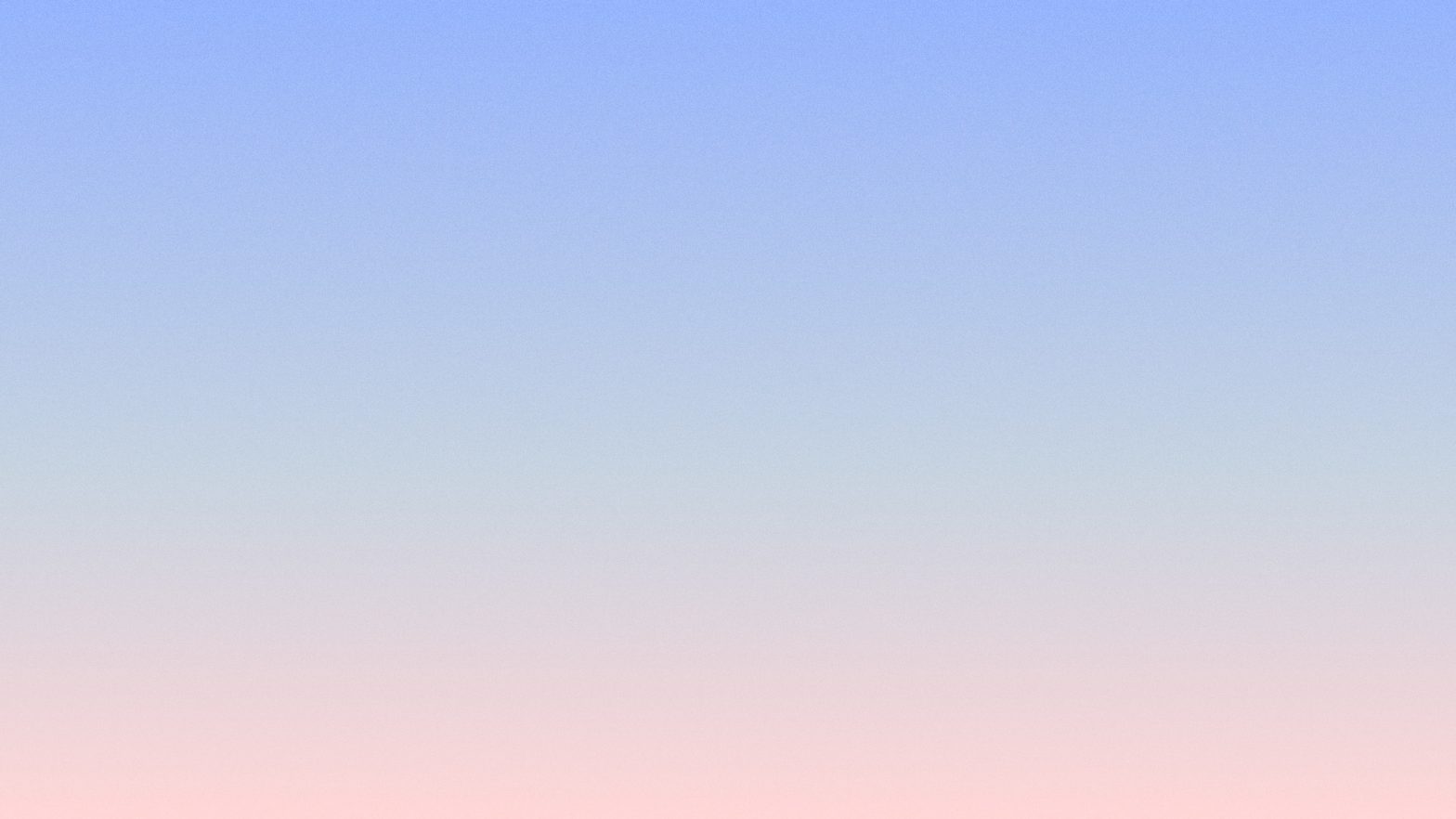デザインに限らず、何事をやるにも技術が要る。その「技」を磨くとはどういうことなのだろうか。遠い昔、科学と技術が未熟であった時代、モノをつくることは神への奉仕ともいうべき特別の行為であり、技を極め、術を知り抜いた一部の人にのみ可能なことで、誰にでも出来ることではなかった。
特別の行為であるからこそ、人はそれが美しく優れたモノになるよう心を込めたのだ。この心の欠けた技術は、それが如何に優れていようと、結果として良いモノをつくり出せないとされた。
心を込めてつくられたモノには、その現れとしての独特の美しさ、風格があるもので、古代の名工の手になる作品が、時代の技術水準をこえて、現代の我々を感動させるのはこのためであろうと思われる。すなわち、「技」を磨くことは「心」を磨くことに他ならないのである。
「技」という字を分解すると、「手」へんに「支」えると書く。「手」はふつう指先から肩口までを指すが、指先、手先、小手先仕事は、悪いことをしたり未熟だったり、気が入らなかったりする仕事ぶりを言う。一般的には素人仕事である。手全体いわゆる腕が使えるようになると、腕前が上がったと言われる。しかし、これでもまだ名人とは言ってもらえない。
「技」ありとは腕(手)を支えているもの、すなわち、「体」を使って事にあたることを言う。体全体でつくったものには気合がこもり、腰が入って勢いのあるものになる。そうすればつくった人の気持ちが相手に伝わる。
こういう力を伝播力といい、また、このように力のこもった商品は商品力が強いと言われる。手先や小手先でやったものは、まず選ばれない。では、どのようにしたら腰の入った仕事ができるようになるのだろうか。
たとえば「学習」という言葉がある。「学ぶ」という字の語源は、真似る、という言葉から来ているそうだ。人は幼いころは両親、長じて先生や先輩の真似をしながら大人になっていく。
「写生」は自然のものをそっくりに写すことを言うし、「模写」は先輩のつくった優秀な作品を正確に再現することを言うが、いずれも徹して真似をすることなのだ。それを一生懸命何度も何度もくりかえしているうちに、なぜ、どうしてというところまで迫っていくことになる。そして自然や優れた作者という、相手の心の中に入っていくことが出来るわけである。
また、「習う」という字の語源は「馴れる」という意味だと聞く。同じことを何度もやるとそのうち馴れてくる。目をつぶっていても出来るようになると、ひとりでに自信がついてくるもの。こういうことを「身につく」とか「板につく」と言う。
身につくというのは、毎日々々着物を上手に着る工夫を繰り返すと、着物と体が一心同体になることから来ている。板につくというのは、能、歌舞伎の世界で練習に練習を重ねると板(舞台)が自分のものになることを言う。こういう風に、優れたお手本を「真似て」体で覚えるまで「馴れる」ことを学習という。
腰が入るようになるには、生半かな努力では出来ない。良い手本を見つけること、学習を重ねること、そして基礎をしっかり身につけることによって出来るものである。その上ではじめてその人なりの、デザイナーならデザイナーなりの個性が創り出されるものなのだ。世阿弥は、「物真似も極まれば独創となる」と言っている。
先に、「技」を磨くことは「心」を磨くことと述べた。たとえば、完璧な水である蒸留水は飲んでも少しもおいしくないのと同様に、「完璧な美」が優れたデザインである保証はない。優れたデザインとは、完璧に美しいものを言うのではないということだ。
優れたデザインには、一見無駄に感じられるような少しばかりの遊び、言い換えるならば自然な色気や人間臭さが必要なのである。人工、完璧、絶対といった言葉の対極にあるものが、自然あるいは人間味というものであろう。
この人には「何か感じる」ところがある、と思われるためには「人間味」や「個性」が必要であることと同じである。デザインにおける遊びは、「美しさ」に人間味を加え、見る人の心を楽しく和ませるものだ。
そして、デザインによって、人の心を引締め緊張させ、あるいは和ませ楽しくさせるのもデザイナーの重要な「技」である。ここにこそ、デザインを行う人が、自らの心を鍛える努力が必要とされる所以があろうかと。「心技一如」と言われる世界である。